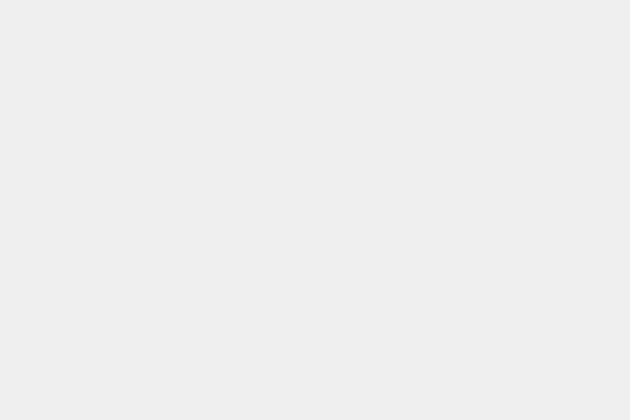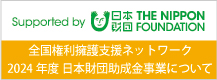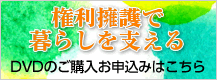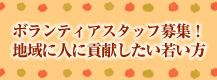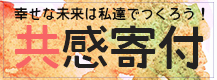包括的代理権
成年後見の改正について、開始と終了の話をしましたが、今回は「包括的代理権」を考えてみます。法律家以外の方は、それなに?、という言葉だと思いますが、今の後見類型の成年後見人が持つ権限がこれです。保佐類型は現在の制度では、民法13条を基本にして限定的に代理権と取消権が保佐人に与えれて、補助類型では、ご本人が選択的に選んで代理権と取消権が付与されますが、後見類型はそんな細かな区別がなく、後見人に包括的に代理権と取消権が付与されます。
なぜこれを考えるかというと法制審議会で、この包括的代理権を付与することを改正法でも例外的に認めてはどうかという議論があるからです。
例外的に認める理由は、個別的に同意を取っていたのでは支援が間に合わない人がいるのではないか、法定後見を利用する人の中にはそういう人がいるのではないか、ということです。ご本人の保護のためには例外的にこれを認めてはどうかという論旨です。皆さんはどう思われますか。これは実質的に後見類型を残すことになります。
実は実務感覚としてですが、この議論は私には分かります。個別の法律行為(契約や不動産移転など)について代理権や取消権を取るのは「めんどくさい」という感覚はあります。「全部、私に任せてくれ」という思いは現場で支援をしている後見人にはかならずあると思います。
ただですね、それは後見人側の思いであってご本人の思いではありません。ご本人の意思を重んじるというのが今回の改正の趣旨であるならば(それは権利条約の趣旨でもあります)、めんどくさいけど、一つ一つご本人の意向を聞くしかないのではないか、そういう議論が当然ででてきますし、こちらが正論だと思います。
ただ現場は辛いですね。いまでも後見類型は扱いやすいけど、保佐や補助は辛いという声は常に聞こえてきます。軽い人ほど大変なんですよ。このことが分かっていない支援者もあちこちにいますけど。
即断はできませんが、来るパブリックコメントでは、両論併記になるのかなあと予想しています。したがってこれにどう意見を言うかが我々の義務になるでしょう。包括代理権なんてものをのこしたら世界の笑いものになるでしょう。