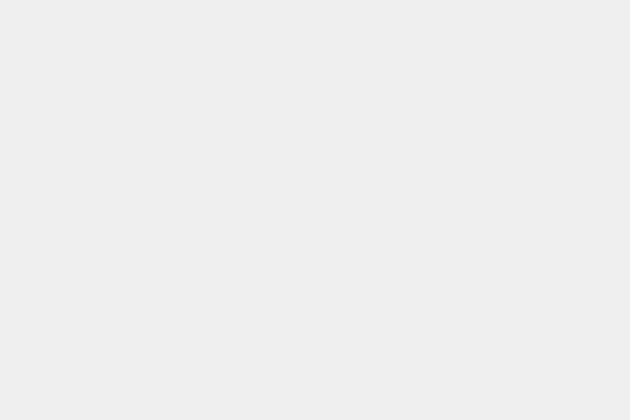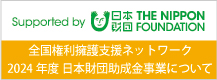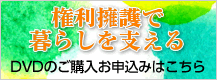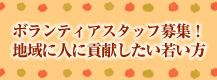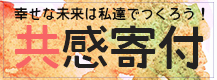権利擁護の旅~平野隆之先生 その①~
権利擁護の旅~平野隆之先生 その①~
https://www.youtube.com/watch?v=B9mYym9Z87s
平野先生は、長らく日本福祉大学で教鞭をとっておられたかたで、日本の地域福祉学の権威です。全国権利擁護支援ネットもたいへんにご指導をいただきました。日本福祉大学に権利擁護研究センターをおつくりいただいて、われわれと月に1回ぐらい共同研究を行っていました。
CLCという全国組織がありますが、最初はそことの関わりがスタートだったそうです。宅老所ですね。地域福祉の当時の研究対象は高齢者だったそうです。
権利擁護研究会の意義については、いわゆる学術一本やりではなくて、社会貢献型の研究センターとして権利擁護研究センターを位置づけておられておられました。これは単に学術的な研究組織ではなくてもっと実践的な活動にフィールドワークが使えるという意味でしょうか。
しかし、福祉の言葉と、法律家の言葉がかみ合わないなかで(しかも実務家と研究者がともに議論する)、大変貴重な研究会であると同時にとても難しい研究会でした。この研究会の成果が「権利擁護がわかる意思決定支援」(2018年・ミネルヴァ書房)でした。
お話の中で「メタ的な現場」という用語を使っておられます。ミクロ・メゾ・マクロとどう違うのかを聞き忘れてしましたが、もちろん違う言葉です。一種のフィールドワークの手法かと思いますが、メタ空間の中でフィールドワークを行うことなのかなあと思っています。そう意味では、権利擁護研究会も平野先生の中ではフィールドワークではなかったのかと思います。
ほかに「せめぎあい」「遅れてくる専門職(後見人のことです)」などなど、ずいぶん刺激的な言葉が飛び交う研究会でした。