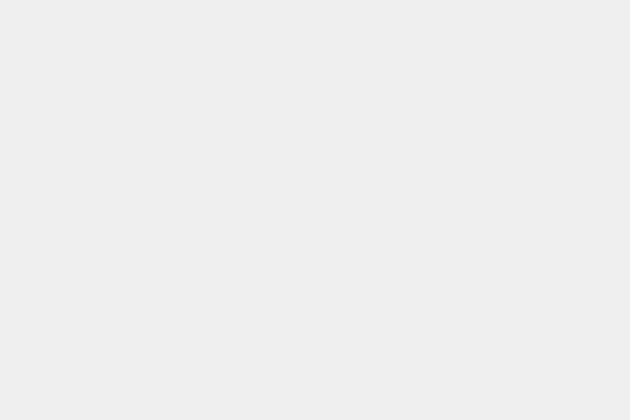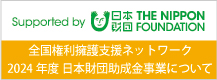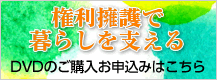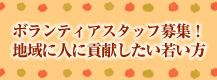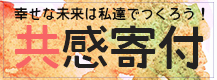任意後見どうする?
成年後見の制度改正の話ですが、今回は、任意後見の改正について
考えます。この話は結構、ややこしいです。
ご存じのことと思いますが、日本の任意後見制度は、世界的な任意後見とは違っていて、似て非なる制度になっています。
どこが違うかというと、任意後見人の職務を開始するためには、任意後見監督人を家裁に選任してもらわなければならないのです。
日本の場合、任意後見契約を候補者と締結し、公正証書にして法務局に登記する手続きをとります。そしてご本人の判断能力が低下したときに後見監督人を家裁に選任してもらって任意後見業務が発効するのが日本の現行制度です。
ずいぶん面倒くさい話になっていますが、世界的にはここまで慎重な制度をとっている国はあまりありません。
なぜ日本がこういう制度をとっているのかは私は正確な事がわからないのですが、やはり任意後見人が不正を行うことを防ぐという趣旨があるのだろうと考えています。
さて、そんな面倒な制度ですが、実際にどれぐらいの任意後見契約が締結されているかというと年間1万件を超えています。
そして、この契約件数の中で後見監督人が選任されているケースは、1割以下です。つまり、契約をして登録をするのですが、ほとんどが任意後見に移行しないで、同時に締結をされている財産管理の委任契約のままで推移しているのです。「移行しない移行型」と呼ばれています。
そこで問題になるのが、ご本人の判断能力が落ちていたら任意後見人候補者が自分の監督人を選任する申立て義務を付けるべきではないか。これがまず一点目です。
つぎに監督人をそもそもつけるべきなのかどうなのか(外国ではつけない例が多いです)、つけるとしても誰が監督人になるのかという点です。
この点を法制審では真剣に議論しているようですが、なかなか議論がまとまらないようです。
現状は以上なのですが、法制審のたたき台では、結構な長文が記載されているので、やはり、ややこしいです。
そこで問題になるのが、ご本人の判断能力が落ちていたら任意後見人候補者が自分の監督人を選任する申立て義務を付けるべきではないか。
これがまず一点目です。つぎに監督人をそもそもつけるべきなのかどうなのか(外国ではつけない例が多いです)、つけるとしても誰が監督人になるのかという点です。
まず誰が監督人になるのか、大きく分けて甲案(現行の規定を変えない)と乙案が議論されています。
乙案では、任意後見監督人の選任を必置とせず、選任しない場合、家裁が直接監督をするという提案や簡易な監督などが提唱されています。
誰も監督をしないという議論はどうもされていないようです。
家裁の直接監督の場合は、家裁の負担は当然増えるわけで、あまり現実的ではないという意見が聞こえそうですね。簡易な監督というのは、その中身がよくわからないのですが、「簡易」とは言え、結局、監督人を付けるわけですから、その報酬負担がご本人に発生するでしょう。
私は「誰も監督をしない」という考え方に魅力を感じるのですが、それだと当然のことながら不正行為が発生します。あるいは親族などとのトラブルが発生します。そうしたトラブル処理を行う機関が裁判所以外には日本には存在しないので、 そうした対応をしないとだめだと思いますが、とにかく「たたき台」ではまったく出てこない議論なのでこれはどうもダメそうですねえ。
次に監督人の選任申立ての義務化ですが、これについても甲案(現行法のまま義務化しない)案と乙案(義務化する)という案がでています。
いまの1割しか申立てされない現状に対する批判を受ければ、乙案という議論になりますが、それだと任意後見候補者の負担が大きすぎるとの意見があるようです。個別の同意を旨とする改正ですから、どの部分について監督人を付けるのか、医師の診断書を用意するのが難しい、といった議論がでています。結局、両論併記のまま結論は先送りになっています。
長文で非常に読みにくい「たたき台」なのですが、受ける印象は、結局、任意後見については、いまとあんまり変わらない話になるのかなあ、というものです。
これについては、評価が二つありうるように思います。「適切な監督人を選任しないで能力の落ちたひとを放置することは保護にかける」これが一つですね。
もう一つは、本人の能力をうんぬんする前に通常の委任契約で支援がおこなれているなら、それはそれで良いではないか」というものです。
重い制度設計をして不正行為を監督すると保護されるかもしれませんが、かろやかに使える制度設計をして、9割の任意後見契約が「移行」しなくてもいいでないか。これは、これは制度設計の「腹のくくり方」の問題です。
ちなみに「親亡きあと」対策としてよく言われる親権者が親権者として子供の任意後見契約を結べるかという問題も
議論もされているのですが、こちらも結論先送りです。
また、任意後見契約と法定後見の優先関係、複数の任意後見契約者いる場合の問題なども議論されていますが、
ちょっと専門的すぎると思いますので、省略します。