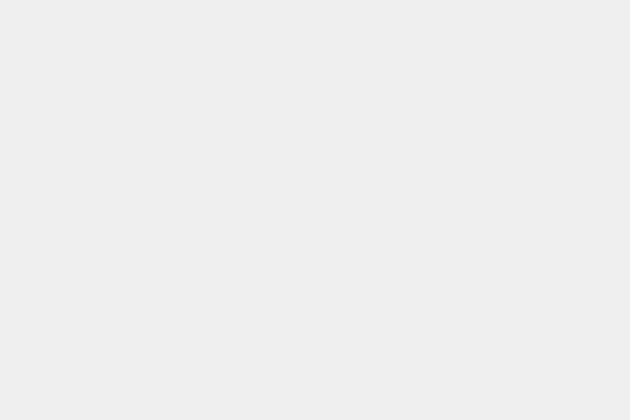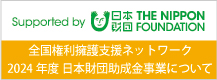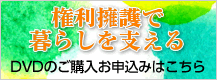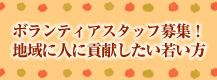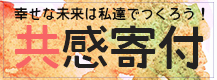意思決定支援は民法に入るのか?
このところ法制審議会の後見制度改革について愚見を披露していますが、今回は、意思決定支援について考えたいと思います。
まず確認です。いま、日本国中、いたるところで意思決定支援という言葉が飛び交っています。みなさんもあちこちで聞いたり話したりされていると思います。
それはそれで良いのですが、日本の民法の条文には「意思決定支援」という言葉はありません。福祉関係の行政法規には、この言葉が入っていますし、促進法の基本計画で全面にでていますが、いわゆる、法律系の基本法(憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、商法)と呼ばれるもののなかにはありません。もちろん司法試験にも出ません。法学部や法科大学院でもごく少数の教授を除けば、まず講義で話すことはありません。
なので法律家は、この言葉についてはまったく知らないのです。権利擁護という言葉も同様です。
数年前に日弁連が、法律家ができる(あるいはしている)意思決定支援についてアンケートを行ったことがありますが、回答の多くは「質問の意味が分からない」というものでした。
そんな中で法制審議会で、成年後見人の意思決定支援が議論されているのです。
どんなことになるのか、容易に予想できるでしょう。
「そんなわけの分からんものを民法に入れることはできない」、こういうことになります。
結局、法制審議会では、この点の審議は満足に行われず(審議する能力がほとんどの委員にないからです)、社会福祉法の改正の場で行われることになるかと思いますが、数点指摘しておきます。
■まず意思決定支援が「わけの分からないものである」という意見は、その通りだということです。
民法にそれでも関係する条文はあります。意思尊重義務というものが民法858条に規定されています。
これは成年後見法ができた時に新たに改正されたものですが、改正するときに民法の教授たちから疑義がだされたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
民法第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほかにこんな条文も関係します。
民法第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これは受任者の義務ですので、直接法定後見に適用できるものではないのですが、民法869条で後見に準用(適用)されています。
さて問題は、ここでいう「被後見人の意思」です。
後見人は、現在の制度では「事理弁識能力」のない人に利用されるものです。つまり「判断能力のない人」の制度なんです。判断能力のない人の意思ってなんでしょうか?。これが成年後見制度発足いらい、謎だらけになってしまっているのです。こんな制度のもとで後見人になる人も利用する人も、なにをどうしていいのか分からないでしょうね。「意思のない人」と制度的に規定されている人に意思決定支援をするのか、それとも代行決定をするのか、現場では混乱するに決まっています。
■意思決定支援という言葉は日本語です(外国語にはなりません)
また「意思決定支援」という日本語のあいまいさが指摘できます。
なぜ自己決定支援と言わないのか。そこでいう「意思」とはなんなのか、「決定」は何をいうのか、どこにも定義や説明がありません。仕方ないので私は私なりの整理をしていくつか書き物にしていますが、ほとんど(少なくとも国内では)参考にされていません。まあ、私の力量のなさですね。
そんなあいまいな言葉を条文の中に置くのはさすがに法律家は躊躇するでしょ。
■でも意思決定支援は重要です(成年後見では無理です)
意思決定支援は、そんな言葉なので法制審でもあまり議論されていませんし、来るパブリックコメントでも民法858条は、いまのまま形で残るのではないかと予想されています。しかし社会福祉法の改正が同時並行的に動いていて、これも成年後見法の改正とほぼ同時期に改正されるのではないかと言われています。2
027年?)。
こちらの内容は前回も紹介しましたが、3月27日の地域共生社会のありかた検討会議で、新日自として議論されています。所管は厚労省で社会福祉審議会で最終的に議論されると思いますが、いままでの日自とは違い、きちんと社会福祉法に位置づけ、金銭管理にとどまらない生活困窮やおひとり様問題も扱う内容になっています。そこでのキーワードの一つが意思決定支援です。成年後見の中ではなくて、地域づくりのなかで意思決定支援を考えていこうという姿勢がでてきています。
どこまで社協がこれに対応できるのかよくわかりませんが、もう少し私も検討してみたいと思っています。全国権利擁護支援ネットワークでは、日自の全国調査を引き続き継続します。
;新たな事業(新日自事業(仮称))について①