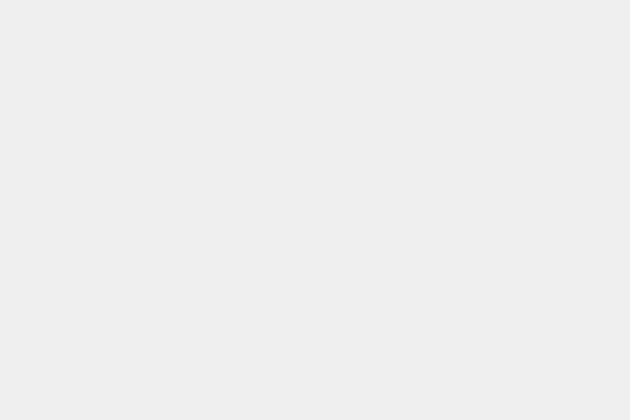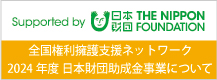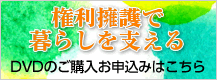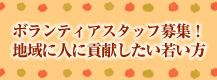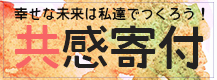権利擁護の旅~平野隆之先生 その②~
権利擁護の旅~平野隆之先生 その②~
https://www.youtube.com/watch?v=oWfbKmZtcv8
権利擁護研究センターの数年に亘共同研究の成果である 権利擁護が分かる意思決定支援という本の解説を語っていただくことから入ります。事例研究とケースワークの間に「事例検討」が入っているところが、醍醐味だそうです。住田さんの事例(胃瘻に反対した事例)、今井さんの事例(精神病院の退院支援)などが俎上にあがってきます。
重層の研究についても解説をいただきます。単なる縦割り解消だったら「包括」で足りる。メゾの平面で事例検討をやろうとすれば「策定委員会」が重要になる。相談支援、参加支援、地域づくりが、策定の中に入るべきで、たんに問題が重なっているから重層とは言えない。三つの層を扱うから重層で、その意味では、8050問題を重層だと言うのは理解が間違っていると指摘されています。
さてその中で、権利擁護支援はどこに入るのか。相談支援ではない。むしろ生活支援(地位福祉)の中に入るのではないか。だから参加支援の中に入るのではないかと指摘されました。
メタの議論とフィールドワークについて再度、解説をしていただきます。メタとメゾの関係が難しいと指摘されています。メゾというのは、なかなかみれない(つまり現場から離れたところのマネージメントは見えない:いわゆる参与観察はできない?)、だから研究会という場で議論して、それぞれが現場に持ち帰るという手法がよい。なかなか難しい話ですね。お話を伺っていて、私がやっている虐待検証はそれなんだと思った次第。とても勉強になりました
中核機関のこれからについてもお話されました。法人後見をやっている団体が中核機関をやることの難しさですね。平野先生は、法人後見の経験のある団体が担うべきだとお話をされました。
このインタビューのあと、新日自の動きはよくわからなことになっていて、中核機関と名乗らないのではないかとか、都道府県社協の事業になっていくのか、そうするとできる社協とできない社協がでてくるのではないかという話がでてきます。平野先生はきちんとそこのところを見ておられます。新日自(という言葉は政府は使わないそうですが)をどうすかという前に、いまの日自をどうするんだという議論が先行しないといけないのではないかと指摘されています。