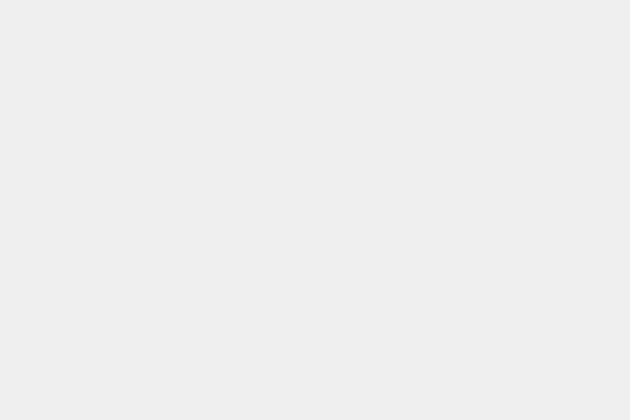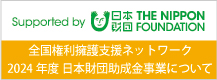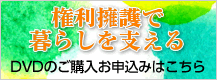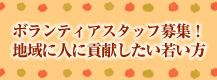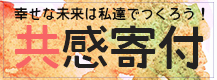法定後見の新制度への移行
成年後見の法改正の問題ですが、これまで、開始、終了、包括的代理権、意思決定支援を取り上げてきました。今回は「移行」の問題を取り上げます。
よく親御さんから、いま申立てをしても新制度ができれば、新制度に移行するのですかと聞かれることがあります。
実は、この問題は法制審では議論されていません。でも大問題であることは委員の間では共有されていると聞いています。
2000年にいまの成年後見制度が成立したときに、それまでの禁治産の利用者は、そのまま自動的に新制度の移行したかというと、そうではありませんでした。だらだらと移行の申請を受けて移行の手続きが進みました。この手続きが行われないと禁治産はそのまま禁治産です。
もともと禁治産の利用はけた違いに少なかったのですし、25年を経た今の段階で禁治産者がいるのかどうのなかもよくわかりませんが、データは出ていません。
また前の制度改正の時は、禁治産は後見類型、準禁治産は保佐類型に「みなす」というみなし規定があったのですが、これは、それぞれ、同じような制度なので「みなす」ことができたのですが、今回はそうもいきません。類型をなくして同意を基本にすえるからです。
そんな中でで、今回の改正で今の成年後見利用者が新制度(改正後の名前が成年後見かどうかもわかりません。成年世話?)、自動的に移行するのか、申請をまって移行するのか、移行しないのか、なにも議論されていないのです。
議論されない、理由は、公表も説明もなにもありませんので、推測するしかありませんが、おそらく「大問題」だからです。なにせ25万人の利用者がいるのです。新制度は、利用者の同意を基本に据えていますから、移行に当たっては同意を取り直すことになるのではないかと思います。
東京法務局の登記事務も大変ですが、この同意の取り直しという作業はどこがやるかと言えば、家裁しか私には考えられません。しかし25万人の同意の確認をいまの家裁の業務のなかで行うのはかなり困難だと思います。
やはりだらだらと移行していくのでしょうが、結構、時間がかかるのではないでしょうか。
そんなわけで、今の段階での申し立ては、よほどの緊急性がない限り極力避けた方が良いというのが私の見解です。そのように親御さんたちにもご説明しています。